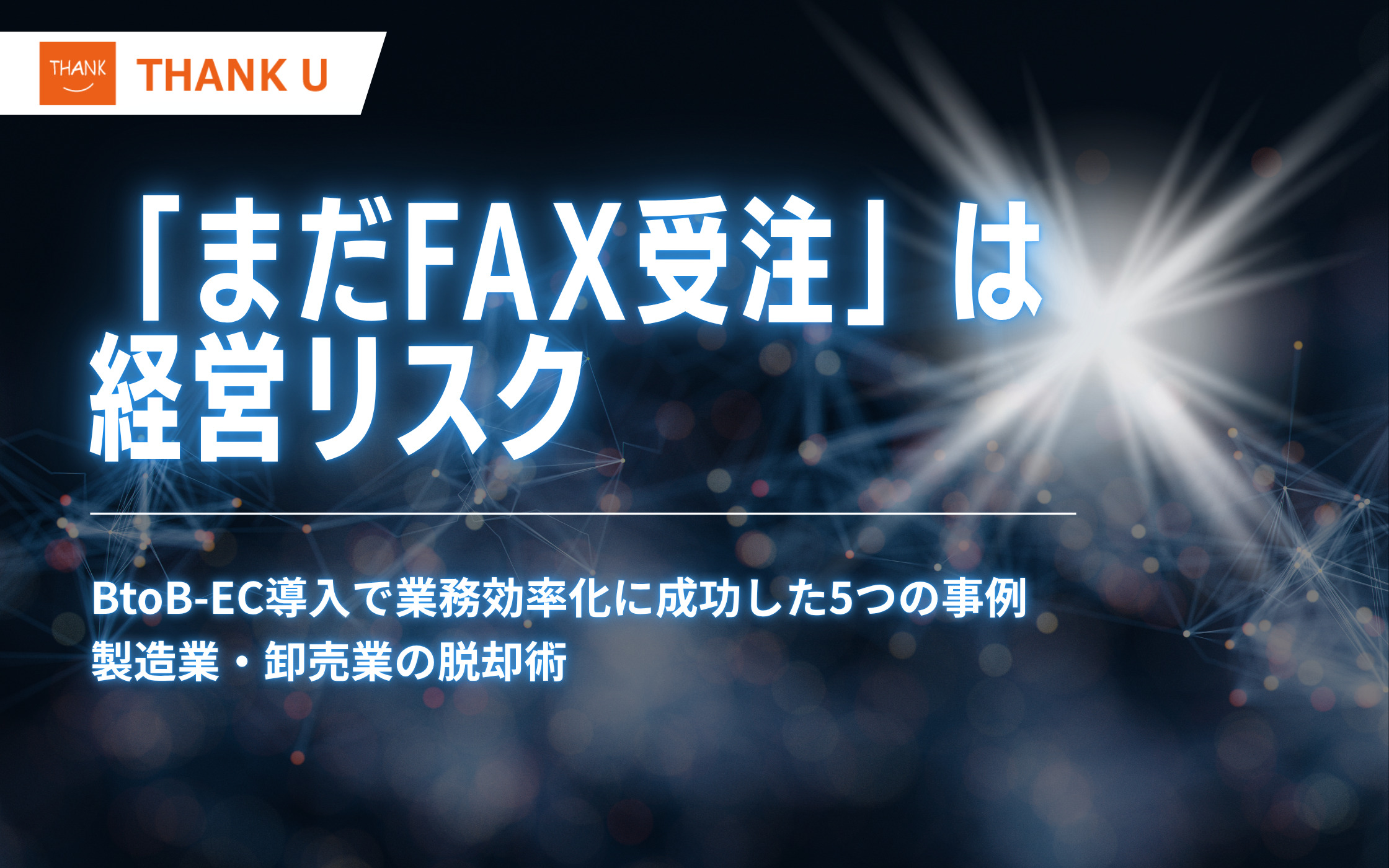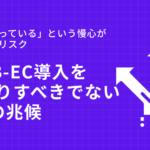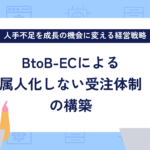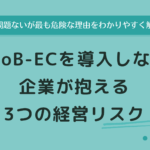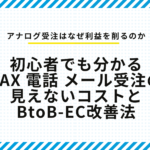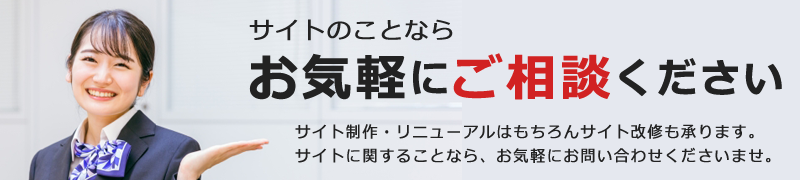はじめに:まだFAXや電話のアナログ受注に追われていませんか?
「お客様との長年の慣習だから」
「ウチの業界は特殊だから、Web化は難しい」
いまだにFAXや電話によるアナログな受注が主流の業界は少なくありません。
特に、製造業・卸売業・印刷業界・医療関連などは、旧来の取引慣習としてFAX注文が根強く残っている傾向があります。
しかし、その「慣習」が、知らず知らずのうちに会社の経営資源を圧迫し、競争力を低下させている可能性があります。
手作業による受注処理は、次のような深刻な課題を生み出します。
- 入力ミス・読み間違い: 手書きの文字が読めず、確認の電話や入力ミスが発生。
誤った商品を出荷し、クレーム対応に追われる。 - 業務の属人化: 「ベテランのAさんしか処理できない」状態になり、業務がブラックボックス化。
退職時の引き継ぎが困難。 - 無駄な管理コスト: 大量の紙の注文書をファイリング・保管する手間とスペースのコスト。
過去の注文を探すのにも時間がかかる。 - 機会損失: 顧客からの「在庫ある?」「納期はいつ?」という電話対応に追われ、営業担当が本来やるべき「提案活動」ができない。
こうしたアナログ業務の課題を根本から解決する手段として、多くの企業が BtoB-EC(企業間取引用ECシステム) の導入を進めています。
本記事では、実際にBtoB-ECを導入して「FAX受注から脱却し、業務効率化と売上向上を実現した5つの成功事例」を、業界特有の課題と解決策にフォーカスして具体的にご紹介します。
事例1:【製造業】FAX受注をEC化し、月40時間以上の残業削減と入力ミスゼロを実現
課題:手書きFAXの「読み間違い」と「手入力」が常態化
ある金属加工メーカーでは、毎日100件以上の手書きのFAX注文が届いていました。
受注担当者は、判読しづらい型番や数量を必死で読み解き、それを基幹システムに一件一件「手入力」していました。
当然、入力ミスや記入漏れも多く、顧客への確認電話や、時には製造ラインでの手戻りも発生し、担当者は疲弊しきっていました。
導入の決め手:クレーム削減と業務標準化
最大の課題は、入力ミスに起因するクレーム対応コストでした。
BtoB-ECを導入し、顧客自身がWeb上で正しい型番と数量を入力する仕組みに変えることで、この問題を根本から断ち切ることを決断しました。
導入後の成果:残業は半減、担当者は本来の業務へ
BtoB-EC導入後、顧客がWebから直接注文できるようになったことで、受注処理のフローは激変。
注文データは基幹システムに自動連携され、手入力作業そのものが消滅しました。
- 顧客別価格やリアルタイムの在庫状況も自動反映。
- 見積依頼もWeb上で完結。
その結果、受注担当者の残業は月平均40時間以上削減され、入力ミスが原因のクレームはゼロになりました。
担当者はクレーム対応から解放され、本来の業務である「生産管理」や「顧客サポート」に時間を使えるようになりました。
事例2:【食品卸売業】「いつもの」注文をEC化し、顧客利便性とリピート率が向上
課題:「前回と同じ」という曖昧な電話・FAX注文
飲食店などを顧客に持つ食品卸の企業では、FAX注文が中心であることに加え、「前回と同じ商品を」「いつものアレを10ケース」といった曖昧な注文が電話で頻発していました。
そのたびに、営業担当者や事務員が過去の伝票を探し出し、内容を確認・入力するという非効率な作業に追われていました。
導入の決め手:顧客の「発注利便性」向上による囲い込み
競合他社も多い中、顧客(飲食店)の発注の手間をいかに減らすかが課題でした。
「発注のしやすさ」で他社と差別化し、顧客を囲い込む戦略としてBtoB-EC導入に踏み切りました。
導入後の成果:売上アップと「提案型営業」へのシフト
BtoB-EC導入により、顧客はマイページから「再注文」ボタンひとつで前回と同じ内容を発注可能に。
スマートフォンの普及もあり、多忙な飲食店の仕入れ担当者が、閉店後や移動中にスマホから30秒で発注を完了できる仕組みが整いました。
- 顧客の発注スピードと利便性が劇的に向上。
- EC化による発注のしやすさが評価され、リピート率が10%以上向上。
- 営業担当が単純な受注作業から解放され、新商品や季節メニューの「提案型営業」に時間を割けるようになり、客単価アップにも貢献しました。
事例3:【印刷業界】複雑なオプション注文と見積対応を自動化し、売上115%を達成
課題:複雑な仕様の確認と見積作成に時間がかかり、失注
印刷会社では、紙質・サイズ・加工方法・色数など、注文のオプションが非常に複雑です。
これらをFAXや電話でやり取りしていましたが、仕様の確認漏れや認識違いが多く、何より「見積作成」に多大な時間がかかっていました。
顧客が価格をすぐに知りたいのに、見積回答が翌日になることもあり、スピード感の欠如が失注の原因になっていました。
導入の決め手:見積スピードの遅れによる「機会損失」の防止
見積の遅れがビジネスのボトルネックであると特定。
顧客がWeb上で完結でき、即時見積が出せる仕組みこそが競争優位になると判断しました。
導入後の成果:工数削減と売上増の「二重の効果」
BtoB-EC導入後は、顧客が画面上で紙質や加工などのオプションを選択すると、自動で見積金額が生成される仕組みを構築。
そのまま発注も可能です。
- 顧客は24時間365日、好きなタイミングで見積取得と発注が可能に。
- 見積対応にかかる社内工数は80%削減され、見積の精度も向上。
- 営業は単なる見積対応から解放され、高単価な企画提案に注力できるように。
結果として、業務効率化だけでなく、顧客の利便性向上による受注増も実現し、社全体の売上は前年比115%を記録しました。
事例4:【医療機器卸】在庫・納期確認の電話をセルフサービス化し、負担軽減
課題:「在庫ある?」の緊急電話が業務を麻痺させる
歯科医院や病院を取引先とする医療機器卸業では、注文時に「この商品の在庫はありますか?」「納期はいつですか?」という緊急性の高い問い合わせが1日に何十件も電話で入っていました。
医療現場は「すぐに答えが欲しい」ため、担当者はその都度作業を中断し、在庫表や基幹システムとにらめっこする必要があり、精神的負担も大きい状況でした。
導入の決め手:顧客(医療現場)の業務を止めないための即時性
顧客の業務(診療)を止めない、スピーディな情報提供こそがサービス品質の核であると定義。
電話対応ではなく、Webによるセルフサービス化が急務でした。
導入後の成果:電話対応半減と顧客満足度の両立
BtoB-ECを導入し、基幹システムの在庫・納期情報をECサイトにリアルタイムで連携。
これにより、顧客はPCやスマホから、欲しい商品の在庫状況と納期目安を即時に確認できるようになりました。
- 請求書や過去の支払履歴もマイページで閲覧可能に。
- 緊急時の注文も24時間受付可能。
結果、定型的な電話対応件数は半減し、受注処理担当者の負担が大幅に軽減。
顧客からも「診療の合間にすぐ確認できて助かる」と高評価を得ています。
事例5:【メーカー】代理店管理をEC化し、バックオフィス全体を効率化
課題:代理店ごとの「取引条件」が複雑すぎた
全国に代理店を持つあるメーカーでは、FAXやメールでの注文処理が煩雑でした。
特に、「A代理店はこの価格」「B代理店はこの掛け率」といった代理店ごとの複雑な取引条件の管理が難しく、経理担当が請求書発行時に手作業で価格を修正するなど、ミスが起きやすい状況でした。
導入の決め手:受注から請求までの一元管理
課題は「受注」だけではなく、「請求」までのバックオフィス全体に及んでいました。
BtoB-ECで顧客ごとの取引条件を管理し、請求までを一気通貫で効率化する必要がありました。
導入後の成果:経理処理の工数も削減し、全社的なDXを推進
BtoB-EC導入により、顧客(代理店)別に異なる価格や取引条件をシステム側で自動反映する仕組みを構築。
- 各代理店は、自社専用のマイページから「自社価格」で注文可能に。
- 注文データがそのまま経理システムにも連携され、請求書発行が自動化。
これにより、受注担当者だけでなく、経理処理の工数も大幅に削減され、社内全体での業務効率化(DX)を大きく前進させることに成功しました。
5つの事例から学ぶ「FAX受注からの脱却」を成功させる鉄則
これらの成功事例には、共通する「成功のポイント」があります。
鉄則1:顧客の「不便」を解消する仕組みを最優先する
BtoB-ECは、自社が楽になるためだけのものではありません。
「再注文機能」「注文履歴の確認」「在庫・納期の可視化」など、顧客(発注担当者)が「便利になった」と実感できる機能を搭載することが、利用促進の最大の鍵です。
鉄則2:自社の「商習慣」に合わせられる柔軟なシステムを選ぶ
BtoB取引では、「顧客ごとに価格が違う」ことが当たり前です。
顧客別の価格設定や掛け率に対応できる、柔軟なカスタマイズ性を持つECプラットフォーム(EC-CUBEなど)を選ぶことが重要です。
鉄則3:基幹システム(販売管理・在庫)と連携させ、「二重入力」を撲滅する
ECを導入しても、その注文データを結局「手入力」で基幹システムに移していては意味がありません。
在庫・受注・顧客情報を基幹システムと自動連携させ、「二重入力」を徹底的に排除することが業務効率化のゴールです。
鉄則4:社内(営業)と社外(顧客)への「利用促進」を徹底する
システムを導入しただけでは、顧客はFAXを使い続けます。
「ECから注文するとポイント付与」「営業担当者からも積極的にWeb注文を案内する」など、社内外を巻き込んだ利用促進活動が不可欠です。
営業担当者にも「受注作業が減るメリット」をしっかり説明しましょう。
鉄則5:スモールスタートで導入し、現場の混乱を防ぐ
いきなり全顧客・全商品を対象にすると、現場が混乱するリスクがあります。
「まずは特定の大口顧客から」「この定番商品群から」といった形でスモールスタートし、成果を確認しながら段階的に対象を拡大していくことが、失敗しないためのコツです。
まとめ:BtoB-ECは「コスト削減」と「未来の売上」を両立する経営戦略
今回ご紹介した5つの事例のように、FAXや電話によるアナログな受注から脱却した企業は、共通して「業務効率化(コスト削減)」だけでなく、「顧客満足度向上(売上・リピート率UP)」という2つの大きな成果を同時に実現しています。
BtoB-ECは単なる受注システムではなく、旧態依然とした業務フローを刷新し、顧客との接点を最適化し、営業・事務の貴重なリソースを「より付加価値の高い仕事」にシフトさせるための「次世代の取引基盤」であり、「攻めのDX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
「ウチの業界はまだFAXが主流だから…」と諦めていませんか?
競合他社が水面下でDXを進めている今こそ、BtoB-EC導入による「業務効率化」と「競争優位性の確保」を真剣に検討すべきタイミングかもしれません。