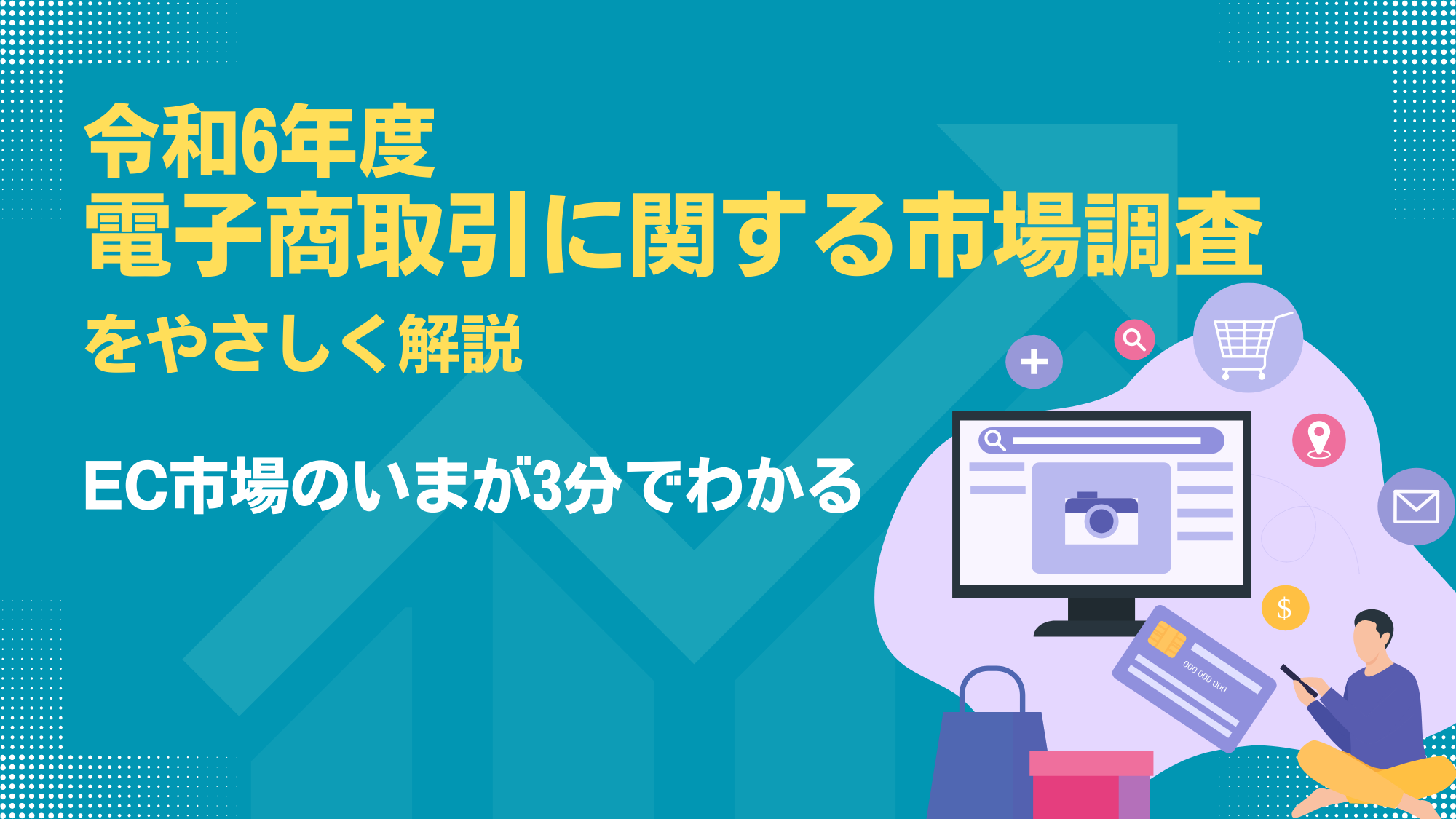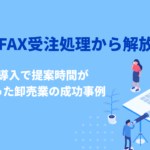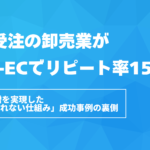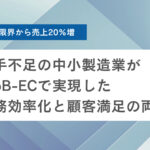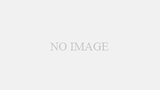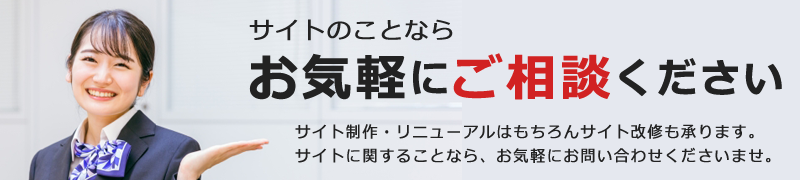令和6年度「電子商取引に関する市場調査報告書」をやさしく要約|BtoC・BtoB・CtoC・越境ECの最新トレンドと実務ポイント
経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」をやさしく要約しました。
BtoC・BtoB・CtoC・越境ECの最新トレンドと、明日から使える実務ポイントをまとめました。
レポートの読みどころを整理
1)BtoC-EC:サービス系がけん引、物販は成熟局面へ
物販系分野は15兆2,194億円(前年比+3.70%)。
EC化率は9.78%へ0.40pt上昇。
伸びは続くが、コロナ期の反動後は鈍化傾向。
サービス系分野は8兆2,256億円(前年比+9.43%)で回復が鮮明。
デジタル系は2兆6,776億円(+1.02%)と横ばい。
3分野合計は26兆1,225億円(前年比+1兆2,790億円)。
「どこで伸びるか」を見誤らないことが重要。
施策の示唆(BtoC)
物販:リプレイスよりも「購入体験の磨き込み(配送最適化・在庫の見える化・レビュー活用)」へ。
サービス:旅行・外食・イベントの予約導線はモバイル前提で高速化(カレンダー・座席・在庫API連携)。
共通:広告は動画・リテールメディアの活用余地が大。
検索×SNS×リテール面を横断で最適化(後述の広告費動向参照)。
2)CtoC-EC:フリマ中心に安定拡大
2024年は2兆5,269億円(+1.82%)。
フリマアプリが主導。
B/Cの混在取引もサイズに含まれる点は理解しておく。
施策の示唆(CtoCに接続する事業者)
リユース連携:公式下取り・査定→EC再販の回遊をつくる。
個人出品者の送料・梱包支援、真贋判定連携で安心感を差別化。
カテゴリ特化のハンドメイド支援は成長余地。
3)BtoB-EC:規模・成長の中心、EC化率43.1%へ
BtoB-EC市場は514兆4,069億円(+10.6%)。
「その他」を除くEC化率は43.1%と、企業間取引の半分近くがオンライン化。
推計ロジックは、法人企業統計の売上高を“分母”、業種別EC化率を“乗算”して2024年の規模を算出する堅実設計。
社内説明に使える。
施策の示唆(BtoB)
既存得意先比率の高い業界は「受発注のEC化」効果が最も大きい(在庫連携・見積→発注→検収→再注文の一気通貫)。
インボイス対応・受発注証跡・権限管理・個別価格・与信管理など“業務要件のEC実装”がKPI。
スマホ利用率の高さから、現場担当が使いやすいUI(QR再注文、発注テンプレ、カタログ短縮URL)を優先。
4)越境EC:3ヵ国(日本・米国・中国)の規模感
日本の越境BtoC(米国・中国向け)合計は4,410億円(米国3,945億円、中国466億円)。
米国向けが大宗。
一方、米国の越境BtoC(日本・中国から)は2兆7,144億円で、日本経由1兆5,978億円、中国経由1兆1,166億円。
中国の越境は5兆7,769億円で市場規模が桁違い。
施策の示唆(越境)
日本発は「米国向け」を主戦場に:決済・物流・返品の体験標準化、英語CSとレビュー運用を最優先。
中国はプラットフォーム戦略が肝。
ライブコマース含む現地文脈での販促設計が必要。
市場を支える“インフラ”の変化
ネット普及・スマホ保有の高さ
インターネット人口普及率は86.2%(2023年)。
横ばいながら、全世代での微増が継続。
世帯のスマホ普及率は90.6%(2023年)。
PC保有率は65.3%まで低下。
モバイル前提のUI/UX設計は必須。
広告投資の伸長
2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円(+9.6%)。
全広告費は7兆6,730億円(+4.9%)と過去最高を更新。
マクロとして“デジタル販促”が増えるほど、ECの集客・CV最適化の継続投資は不可避。
現場で役立つレポートの“定義”メモ(社内共有向け)
ECの要件:受発注がコンピューターネットワーク上で行われる取引のみを算入(決済手段は不問)。
見積等の前段階のやりとりは含めない。
BtoC-ECにはCtoCやGtoCは含めない(販売サイド金額で把握)。
BtoB-EC推計:業種別売上(分母)×EC化率(伸び率補正)で2024年規模を導出。
指標の説明責任に耐える。
2025年に向けた“やることリスト”
BtoC事業者
物販:レビュー生成・在庫連動・ロイヤリティ(サブスク/会員)でLTV設計。
サービス:予約UIの秒速化(カレンダー直結、残数表示、Apple/Google Wallet連携)。
計測:広告×CRM×リテールメディアの横断アトリビューション。
BtoB事業者(とくに製造・卸・印刷など)
基盤:個別価格・見積承認・与信・インボイス・納期/在庫APIの“業務要件”をEC上に移植。
運用:再注文導線(履歴1クリック・QR・CSVアップロード)で定期発注を自動化。
現場:スマホ前提のUI、担当者別権限、得意先ごとの商品・価格・見積フォーマット。
目的:商談の“無駄な往復”を除去し、営業は提案・深耕に注力できる体制へ(ECは販促ではなく“受発注の標準装置”)。
まとめ:伸びるところに投資しつつ、BtoBは“業務EC”で差がつく
BtoCはサービス系の伸びを取りにいく。
物販は買い物体験と在庫・配送の磨き込みが主戦場。
CtoCはリユース/ハンドメイドで需給を広げる余地大。
そしてBtoBは“規模×伸び”の本丸。
EC化率43.1%の世界では、仕様×運用の実装力が企業競争力に直結する。
参考(一次情報)
本記事は経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(令和7年8月公表)をもとに要約・解説しました。
原典の主要図表・定義・推計ロジックは本文中の該当箇所を参照ください。