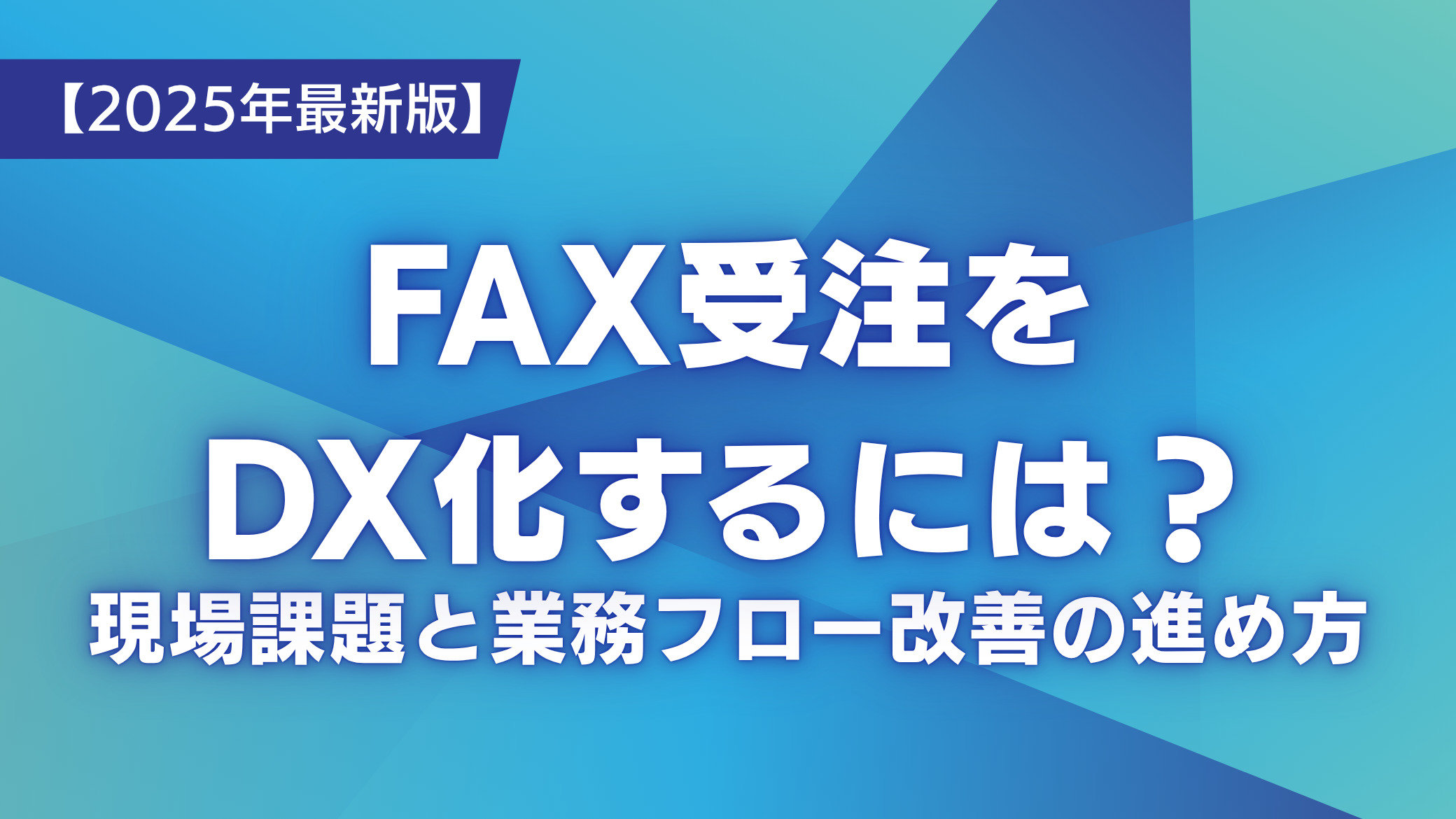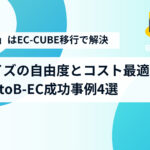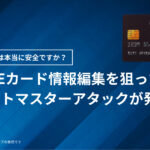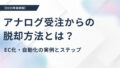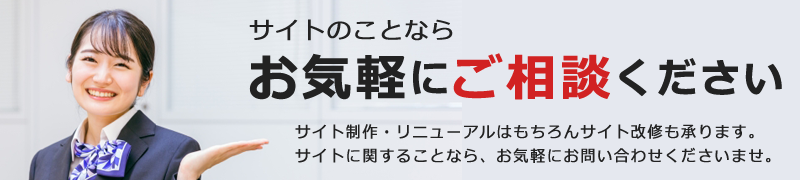はじめに:FAX注文のDX化は「紙をやめる」ことではない
DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が一般化する中で、多くの企業がFAX注文業務の見直しを迫られています。
特にBtoB取引においては、「FAXでの注文が当たり前」という文化が根強く残っており、システム化の遅れが業務効率の足かせとなっているケースも少なくありません。
しかし、FAX注文のDX化”とは、単にFAX機や紙を廃止することではありません。
本質的な目的は、「アナログな受注業務をデジタル化し、業務全体を効率化・標準化すること」にあります。
FAXという手段に固執している背景や現場の課題を理解しながら、現実的なステップで受注業務を最適化していくことが必要です。
本記事では、FAX注文をDX化するための具体的な進め方や、導入企業が得られる効果、活用できるツールの選定ポイントをわかりやすく解説します。
なぜFAX注文はなくならないのか?現場が抱える4つの課題
FAX注文のDX化に踏み切れない企業には、それなりの理由があります。
単なる慣れやアナログ志向では済まされない、実務上の課題が存在しているのです。
以下に、現場でよく見られる4つの課題を紹介します。
① 顧客がFAXを使い続けている
「取引先がFAXじゃないと困る」「メールやECサイトに対応していない顧客が多い」といった理由で、FAX対応を続けざるを得ないケースがよくあります。
特に高齢の担当者が多い業界や、地域密着型のビジネスではFAX文化が根強く残っており、顧客起点でのDX推進が難しいというジレンマがあります。
② 注文書の書式がバラバラ
FAXで送られてくる注文書は、企業ごとに様式が異なり、統一性がありません。
手書き・押印・略語・記号なども多く、読み取りに時間がかかるだけでなく、入力ミスや認識違いの原因にもなります。
DX化を進めるには、これら多様なフォーマットへの対応が避けて通れません。
③ 受注処理が属人化している
FAXを見て注文を処理する業務は、長年同じ担当者が慣れ”で対応しているケースが多く見られます。
特定の人でないと内容が読み取れない・判断できないという状況は、業務のブラックボックス化や引継ぎ困難といったリスクを生み出します。
属人化の解消はDX化の第一歩です。
④ 他業務との連携ができない
FAXで受けた注文内容は、手入力で販売管理システムや会計ソフトに転記されるのが一般的です。
この手作業がある限り、受注から出荷・請求に至るプロセスは分断され、在庫や納期の確認・帳票作成に時間がかかります。
システム連携を前提としたDX化が必要です。
こうした現場の実態を正しく把握したうえで、「いきなりFAXをやめる」ではなく、「FAXを前提とした仕組みを段階的に見直す」ことが現実的なアプローチです。
FAX注文のDX化で得られる5つのメリット
FAX注文のDX化を実現することで、単に「紙がなくなる」だけではなく、企業全体にわたる業務改善が可能になります。
ここでは、実際の導入企業が実感する主な5つのメリットをご紹介します。
① 入力作業の工数削減
FAXで受けた注文書を販売管理システムに手入力する作業は、1件あたり数分〜十数分かかることも珍しくありません。
DX化によってOCRや自動取込が可能になれば、1件あたりの処理時間を1/3〜1/10に短縮できます。
繁忙期や人手不足でも処理能力を維持できるようになります。
② ミス・トラブルの削減
FAXの読みにくさや誤解、転記ミスによる商品間違い・数量違いなどは、出荷ミス・納期遅延・請求誤りなどのトラブルにつながります。
DX化で情報を正確にデジタル化することで、人為的ミスを大幅に削減でき、クレーム対応コストの削減にもつながります。
③ 属人化の解消・業務の標準化
手書き注文の解釈や、顧客ごとの個別ルールに対応していたベテラン頼みの業務”も、DXによってデータとして残り、誰でも同じルールで処理できる仕組みへと変わります。
引き継ぎも容易になり、離職や異動による業務停滞を防げます。
④ 顧客対応スピードの向上
注文内容が自動でシステムに反映されることで、在庫の確保、納期回答、出荷手配などが迅速化されます。
これにより、顧客満足度が向上し、競合との差別化にもつながります。
ECサイトとの連携により、ステータスの可視化も実現できます。
⑤ 経営・業務データの可視化
FAXでやりとりしていた情報がシステム化されることで、どの顧客がいつ何をどれだけ注文したかといった受注データを正確に蓄積・分析できます。
これにより、販売傾向の把握、在庫最適化、業務改善のPDCAも回しやすくなります。
現場に無理なく導入するDXのステップ
FAX注文のDX化は、一足飛びにECサイトへ全面移行するのではなく、「現場の負担を最小限に抑えながら段階的に進める」ことが成功のポイントです。
以下に、無理なくDX化を推進するための現実的なステップを紹介します。
ステップ1:FAXをPDFで取り込み、OCRでデータ化
まずは、紙のFAXをスキャンしてPDF化し、OCR(文字認識)ツールで読み取り、データに変換する工程からスタートします。
これにより、アナログな帳票からでも受注データをシステムに取り込む準備ができます。
手入力の手間を削減する第一歩です。
ステップ2:定型の注文フォーマットに統一してもらう
OCRでの自動処理精度を高めるため、取引先にあらかじめ提供した「注文書テンプレート」を使ってもらうのも有効です。
書式が統一されれば、読み取り精度が上がり、業務フロー全体が安定します。
印刷してFAXしてもらう形式でも構いません。
ステップ3:OCR結果をRPAでシステムに登録
OCRで読み取った注文情報を、販売管理や会計システムに登録する工程をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化することで、さらに業務効率化が進みます。
人手による転記が不要になり、入力ミスも激減します。
ステップ4:BtoB-ECの併用で将来的な移行も視野に
FAXでの注文が多くても、並行してWeb注文にも対応することで、一部の顧客や製品群をECサイトで受けられるようになります。
最終的にはEC化を進めつつ、FAXとのハイブリッド運用で段階的に移行する設計が理想的です。
このように、業務の現実に即したムリのないDX”を選択することが、FAX受注の脱却につながります。
ツール選定のポイント|OCR・RPA・ECの違いとは?
FAX注文のDX化を進めるにあたり、「どのツールを選ぶべきか」は非常に重要なポイントです。
企業によって既存の業務フローやITリテラシーが異なるため、すべての業務に一つのツールで対応しようとするのは現実的ではありません。
以下に、代表的な3種類のツールの特徴を整理します。
① OCR(光学文字認識)ツール
- 紙やPDFで届いた注文書を画像解析し、文字情報に変換
- 帳票のレイアウトや文字のクセに影響を受けやすい
- 最近はAI-OCRの精度が向上し、手書き文字にも対応可能
向いている企業:「まずは入力作業を効率化したい」「顧客がFAXをやめられない」「書式がある程度統一されている」場合に適しています。
② RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
- OCRで抽出したデータを、基幹システムに自動入力
- 決まった画面操作を人の代わりに実行できる
- 処理対象が定型であるほど効果を発揮
向いている企業:「基幹システムがAPI非対応」「定型的な業務が多い」「IT改修に時間がかけられない」場合に向いています。
③ BtoB-ECシステム(受発注Webシステム)
- 注文内容を顧客自身がWeb上で入力・送信できる
- 在庫・価格・履歴などもオンラインで確認可能
- 将来的な受注プロセスの標準化を目指せる
向いている企業:「一部の顧客はデジタルに移行できそう」「今後FAX脱却を目指す」「受注ミスを根本から減らしたい」企業に適しています。
これらのツールを単体で使うのではなく、段階に応じて組み合わせて使う(OCR→RPA→EC化)ことが、FAX業務からのスムーズな脱却に有効です。
現場が前向きに取り組める巻き込み方”
FAX注文のDX化は、ツール導入だけでは成功しません。
実際に運用する現場担当者の協力と納得感があって初めて、継続的な改善と定着につながります。
ここでは、現場を巻き込む3つのコツをご紹介します。
① 小さな成功体験をつくる
いきなり大きな変化を押し付けると、現場の反発を招くことがあります。
まずは一部の取引先・商品・部門から始めて、成果(例:処理時間が半分に!)を見える化”し、「便利になった」という実感を広げましょう。
② 目的とゴールを明確に伝える
「FAXをやめたい」「業務改善のため」といった抽象的な説明だけではなく、「毎日●件の入力を減らす」「属人化を防いで引継ぎをスムーズにする」など、現場にとっての直接的なメリットを丁寧に伝えることが大切です。
③ 業務設計の主役”として関わってもらう
改善施策をトップダウンで決めるのではなく、現場の声を反映して設計することで、運用後のギャップが小さくなり、現場のモチベーションも高まります。
担当者をプロジェクトチームの一員として巻き込むのがおすすめです。
このように、業務のユーザー”である現場をしっかり巻き込みながら進めることで、FAX注文のDX化は無理なく、継続可能なものになります。
まとめ:FAXから始まる現場DX
FAX注文のDX化は、「紙をなくす」「FAXを捨てる」といった表面的な改革ではありません。
真の目的は、受注業務全体の効率化・標準化・可視化を実現し、社内外の業務品質を高めることにあります。
特に中堅・中小企業では、いきなり100%のデジタル化は難しい場合も多いですが、OCRやRPAを活用した段階的なDX化で、「今のFAX文化を尊重しつつ、未来に向けた改善」が可能です。
以下のような姿が、DX成功の一つのモデルです:
- 顧客は変わらずFAXで注文 → システム側で自動処理
- 手入力は不要に → 業務が標準化・高速化
- 分析できる受注データが蓄積され、経営判断にも活用
まずは一歩ずつ、現場に合った形でDXを始めてみませんか?
FAX業務の改善から、会社全体の業務変革は始まります。
関連記事

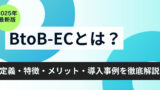


投稿者プロフィール
- CEO
- 関西大学卒業後、東証プライム上場企業ゼネコンにて人事総務業務に従事。
幼少よりモノ作りが好きだったこともあり、「モノを作る仕事がしたい」という思いからシステムベンダーへ転職。
システムベンダーでは、IBMオフコンAS400で金融、物流、販売管理、経理、人事総務などのシステムを開発。
台北に駐在し遠東國際商業銀行のシステム構築プロジェクトへの参画など貴重な経験を積む。
10年間で、プログラマ、SE、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーを務め、「システムの質は要件定義の質に比例する」と学ぶ。
その後、クレジット決済代行会社にヘッドハンティングされる。
決済システムの再構築、国内外の銀行システムとの接続、クライアントの会社サイト制作・ECサイト構築を行う。
一方、組織改革を任され、20名から60名へ会社規模を拡大させる。(退任時役職:常務取締役)
2008年クリエイティブチーム・サンクユーを立ち上げ、2010年に法人化し株式会社サンクユーを設立。
クライアントの業界、取扱商材、ターゲット顧客を理解・分析することで、結果が出るWEBサイトを制作することを得意とする。
また、ECサイト構築・運営への造詣も深く、NTTレゾナント株式会社が運営するgoo Search Solutionでコラムを執筆。
ECマーケティングレポート | goo Search Solution
■趣味・好きなもの
BMW / WRC / ロードバイク / RIZIN / Bellator / UFC
David Bowie / blur / MUSE / TheRollingStones / XTC
機動戦士ガンダム(ファースト) / 富野由悠季
ベルセルク / 頭文字D / 進撃の巨人 / ジョジョの奇妙な冒険 / あしたのジョー
Mission: Impossible / Memento / ワイルド・スピード / ソナチネ
LOST / Game of Thrones / FRINGE / The Mentalist
上岡龍太郎 / ダウンタウン